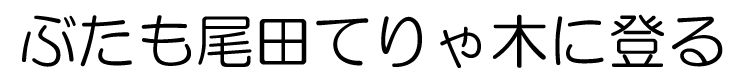本番の神様
さとしは学校へ行くのが憂鬱でした。
「全部、あきよちゃんが悪いんだ。」
毎朝、ぶつぶつ言いながら、さとしは学校へ向かうのでした。あの日のことを思い出すたび、腹が立ちます。
「ねえねえ、大ニュース!」
三学期が始まったばかりのある日、みんなで給食の準備をしていると、みさとが走って教室に入ってきました。
「廊下は走っちゃいけないんだぞ。」
学級委員のしょうたが注意しても、みさとは全く聞いていません。
「みか先生、赤ちゃんが生まれたんだって!」
ええーっとクラスじゅうが大声を上げました。みか先生は、さとしたちの担任の先生で、今、産休をとっています。みさとの話によると、みか先生は元気な女の赤ちゃんを産んで、無事退院したそうです。
「それでね、みか先生、音楽会は聞きに来るらしいよ。」
「赤ちゃんも一緒かなあ。」
「見たい見たーい!」
みんな、給食も忘れてはしゃいでいます。突然、あきよの良く通る声が教室に響きました。
「いいこと考えた!」
全員が一斉にあきよのほうを振り返りました。
「音楽会で優勝して、みか先生をびっくりさせようよ。」
さとしの小学校では、三学期の終わり頃に、クラス対抗で優勝を競う音楽会があります。みか先生は音楽が好きで、器楽クラブの顧問もしていたのです。
「それ、いいね!」
みさとが賛成しました。さとしは黙っています。音楽はちょっと苦手なのです。でも、そんなことにはおかまいなしに、あきよは続けました。
「毎日放課後にみんなで残って練習しようよ。絶対優勝できるよ。」
クラスで一番体の大きいともきが、
「嫌だよ、そんなの。」
と面倒くさそうに言いました。ともきはサッカーや野球は得意ですが、音楽には興味がないのです。他にもいろいろな意見が出て、給食の時間は大騒ぎとなりました。結局、多数決で「みか先生のためにがんばって優勝する」ことが決定しました。そして、さとしのクラスは、他のクラスよりちょっと難しい曲を選んだのです。
● ● ●
今日も、放課後にクラス全員が音楽室に残り、練習が始まりました。さとしは、じゃんけんでハーモニカの担当になったのですが、それは重要なパートだったのです。曲のなかに、他のみんなが伴奏をして、さとし一人だけがメロディを吹く部分があります。さとしはその部分が上手く吹けなくて大嫌いなのです。今日の練習でも、その部分に差し掛かると、やっぱり間違えて曲が止まってしまいました。
あきよが、弾いていたピアノをバンと叩いて立ち上がり、大きな声で言いました。
「ちょっと、さとしくん、まじめにやってよ。いつも間違えてるじゃない。」
あきよは幼稚園の頃からピアノを習っているので、とても上手なのです。さとしはむっとしました。
「できないものは、できない。」
「練習してないんでしょ。」
「あきよちゃんなんか、ずるいじゃないか。小さいときから習ってたら、ぼくだって練習しなくたってできるよ。」
あきよの顔色がさっと変わりました。
「そんな言い方はないでしょう。何も知らないくせに!」
「そっちこそ、自分が上手いからってバカにして!」
さとしは譜面台を蹴っ飛ばして音楽室を飛び出しました。
さとしは、まっすぐ家に帰る気になれず、学校の近くの公園でベンチに座り、空を睨みつけていました。
「さとしくん、どうしたの?」
声を掛けたのは、加藤さんでした。加藤さんは、さとしと同じ町に一人で住んでいるおじいさんです。町内会の行事があると、よくギターを弾いてみんなの歌の伴奏をしたりするので、近所ではちょっとした有名人です。
加藤さんは大きなギターケースを肩から降ろして、さとしの隣に腰掛けました。婦人会などに依頼されて演奏しに行くことがちょくちょくあるそうなので、今日もそんな演奏の帰りなのに違いありません。
さとしが音楽会のことを話すと、加藤さんは、
「ちょっと譜面を見せてごらん。」
と言いながらギターを取り出すと、旋律だけでなく伴奏も付けて、さらりと弾いてしまいました。
「すごい! 加藤さんって天才?」
旋律しか書いていない譜面なのに、伴奏を付けて弾くなんて、まるで魔法のようだとさとしは思ったのです。
ハハハと加藤さんは笑いました。
「実はこっそりカンニングをしたんだよ。ここに、Amとかって記号が書いてあるだろう。これを見れば、どんな伴奏を付ければいいのかすぐわかるのさ。それより、ここの旋律、とってもかっこいいね。」
さとしはちょっと不機嫌になりました。加藤さんが指さしたところは、さとしの一番嫌いな、自分だけがメロディを吹くところだったのです。
「そうか、ここがさとしくんのソロなのか。責任重大だなあ。」
「こんなの、絶対にできっこないよ。」
「なあ、さとしくん。もし良かったら、一緒に練習しないかい? いつでもうちにおいで。」
● ● ●
加藤さんは、もうかなりおじいさんだけど、結婚もしていなくて、古いアパートに一人で住んでいます。若い頃はギターの名人で、いろんな演奏会に出ていたという話を、さとしも聞いたことがあります。前にさとしのお母さんが「加藤さんって、オーケストラをバックに、ソロを弾いたこともあるらしいよ。聞きたかったなあ。」と言っていたけど、オーケストラが何なのかよくわからなかったので、そのまま忘れていました。加藤さんの部屋には、「なんとかコンクール優勝」などと書いてあるトロフィーが数えきれないほどたくさんあるのですが、それらは全然大事そうにではなく、どうでもいいみたいにぐちゃぐちゃに置いてあり、ほこりをかぶっているのでした。
加藤さんは、さとしに最初から最後まで、ひととおり曲を吹かせてみると、言いました。
「さとしくんは、赤ちゃんの時から速く走れたかい?」
いきなり変なことを聞くなあと思いながら、さとしは、
「そんなわけないじゃん。ハイハイして、立って、歩いて、それから走れるようになるんだよ。最初から速く走れるわけないじゃないか。」
と答えました。
「そうだろう。楽器も同じなんだよ。最初はゆっくりから練習しなくちゃ。ギターで遅いテンポで伴奏するから、そのテンポに合わせて丁寧に練習してごらん。」
それはあまり楽しい練習ではなかったけれど、何度もやるうちに、いつも同じ場所でテンポが狂うことがわかってきました。譜面に印を付けて、そこに気をつけながら吹いてみると、加藤さんが「お、良くなった」とか「そう、その調子」とか褒めてくれます。さとしは、音楽会までの間、なるべく加藤さんの家に行って練習してみることにしました。
● ● ●
加藤さんと一緒に練習するようになって、二週間がたちました。でもやっぱり学校では、いつもさとしのソロのところでリズムがおかしくなってしまいます。
「またさとしかよ、しっかりしろよ。」
ともきが文句を言います。ともきは、練習を早く終えてサッカーをやりたいのです。しょうたも、
「本当に大丈夫なの?」
と心配そうです。さとしはきまりが悪くてうつむいています。他のみんなも、ざわざわし始めました。
「みんな静かにして。さとしくん、今のところ、吹かずにちょっと聞いててくれる?」
あきよが、その場所の少し前から、ピアノを弾いて見せました。
「リズム、わかったよね。ピアノを聞いてリズムをとってから、吹き始めてみて。」
さとしは、あきよにいつも注意されて、がっかりするのでした。
一生懸命練習しているのに、どうしてちゃんと吹けないんだろう。
● ● ●
加藤さんが教えることは、さとしが初めて聞く練習方法ばかりでした。たとえば、
![]() を
を
![]() というように、タッカタッカのリズムで練習したり、
というように、タッカタッカのリズムで練習したり、
![]() とタラータラーと伸ばして練習したりしました。それから、後半の
とタラータラーと伸ばして練習したりしました。それから、後半の
![]() だけを何回か練習して少し上手にできるようになってから、
だけを何回か練習して少し上手にできるようになってから、
![]() と全部をつなげて練習してみたりしました。そんな練習はやっぱりあまり楽しくなかったけれど、加藤さんの言うとおりにやってみると、「すごくむちゃくちゃ」だった演奏が、「少しむちゃくちゃ」くらいには改善されるのです。ひょっとしたら音楽会に間に合うかもしれないと、さとしは思い始めました。
と全部をつなげて練習してみたりしました。そんな練習はやっぱりあまり楽しくなかったけれど、加藤さんの言うとおりにやってみると、「すごくむちゃくちゃ」だった演奏が、「少しむちゃくちゃ」くらいには改善されるのです。ひょっとしたら音楽会に間に合うかもしれないと、さとしは思い始めました。
あるとき、さとしはふと気がつきました。自分が速くなったり遅くなったりしても、加藤さんのギターはぴたりと自分の吹くリズムに合っているのです。あきよのピアノとは、いつもずれて曲がわからなくなってしまうのに、です。不思議に思って聞くと、加藤さんは逆に聞きました。
「さとしくんは、あきよちゃんと仲良しなのかい?」
「あんな女、大っ嫌いに決まってるじゃないか。」
さとしが本当に嫌そうな口調で言うと、加藤さんは悲しい顔をしました。
「それじゃ合うわけがないよ。音楽はね、心で合わせるものなんだ。誰だって嫌いな人に合わせることなんてできないさ。うーん、困ったなあ。どうしようねえ。」
加藤さんは、本当に困ってしまったようでした。そんなこと言ったって、嫌いなんだからしょうがないじゃないか、とさとしは心の中でつぶやきました。でも、自分のために困っている加藤さんを見ると、なんだか申し訳ないような気がしたのでした。
● ● ●
いつものように加藤さんの家で練習した帰り道、さとしがソロのフレーズを口ずさみながら角を曲がると、むこうから走ってきた人と正面からぶつかってしまいました。お互いにはじかれるように転び、その拍子に相手の持っていた手提げが落ちて、中身がばらばらとこぼれました。
「ごめんなさ・・・・・・」
さとしは言いかけてびっくりしました。よろよろと立ち上がった相手は、あきよだったのです。そして、もっとびっくりしたことに、あきよは目を真っ赤にして、顔じゅう涙でぐしゃぐしゃだったのです。
「あきよちゃん!?」
さとしが声をかけるよりも早く、あきよはものすごい勢いで走り去ってしまいました。さとしは呆然としました。あきよとは昨年度から同じクラスだけど、泣いたところなんて一度も見たことがなかったのです。
さとしは、あきよが落としていった手提げと、散らばった中身を拾いました。それはピアノの譜面でした。一瞬真っ黒に見えるくらい、たくさんの音符がぎっしりと並んでいます。拾い集めながら、明日学校で渡そうと考えましたが、ともきたちに見られたら何を言われるかわからないと思い直し、そのままあきよの家へ向かったのでした。
「まあ、わざわざありがとうね」
玄関のベルを鳴らすと、あきよのお母さんが出てきて、何度もお礼を言いながら手提げを受け取りました。
「あきよが出てこなくてごめんなさいね。今日のレッスン、うまく弾けなくて先生に叱られたらしいの」
さとしは驚きました。あきよに弾けないことがあるなんて信じられません。
「寒いのにありがとうね。気をつけて帰ってね」
あきよのお母さんに丁寧に見送られて、さとしは暗くなった道を急ぎました。
● ● ●
次の日、さとしがひとりでいる時を見計らったように、あきよが近づいてきました。
「昨日はありがとう」
あきよはうつむいたまま言いました。
「いや、その・・・・・」
さとしが言いよどんでいると、あきよは突然、きっと顔を上げてさとしをまっすぐ見つめました。
「泣いたけど、負けてないんだから。絶対、あきらめないんだから」
あきよはくるりと踵を返すと行ってしまいました。
さとしはまたもや呆然と、その後ろ姿を見送ったのでした。
● ● ●
その日は雪がぱらついていました。さとしは、加藤さんの家へ行くのを迷いましたが、一人でやるより加藤さんと練習する方がいいような気がして、出かけたのでした。そして、その日はとても良い日になったのです。
「できた!」
さとしは自分でも驚きました。初めて、ソロを最初から最後まで、間違えずに吹くことができたのです。
「すごいじゃないか、良く頑張ったね。」
加藤さんも嬉しそうです。
「あきらめずに、たくさん練習したからできたんだよ。」
その時、さとしの頭に、先日のあきよの泣き顔が浮かびました。さとしはずっと、あきよは昔からピアノを習っているから、どんな曲も苦労せずにすらすら弾けるのだと思っていました。だから初めてあきよに注意された時、「ずるい」と言ってしまったのだけれど、それを聞いてあきよが掴み掛からんばかりに怒っていたわけが、今になってわかります。
「上手な人は、練習したから上手だったんだね。あきよちゃんに悪いこと言っちゃったなあ。」
加藤さんは、にっこりと頷きました。
そういえば、さとしは一度だけ、加藤さんに怒られたことがあります。加藤さんの家でトイレに行きたくなって、間違えて別の部屋のドアを開けようとした時のことです。普段は穏やかな加藤さんが、きつい口調で、「そこは開けてはいけない」と大声を出したのです。さとしはびっくりしました。すぐに加藤さんは「驚かせてすまなかった」と謝り、いつものやさしい顔に戻ったのですが、それ以来、さとしはその部屋には絶対に近づかないようにしていました。
● ● ●
音楽会まで、あと一ヶ月を切りました。練習にもいっそう熱が入ります。でも、いつまでたっても、さとしは曲がソロの部分に近づくと、心臓がバクバクして、身体がカチコチに固まってしまうのです。途中までなんとかうまくいっても、後半で失敗してしまったりします。さとしは、その度にがっかりしてしまうのです。
そんなある日、下駄箱で靴を履き替えていると、柱に隠れるようにあきよが立っているのが見えました。あの一件以来、お互いに避けるような感じになっていたので、さとしはどきんとしました。あきよはためらいがちに二、三歩近づき、大きく息を吸うと、
「がんばって練習してるみたいじゃん。良くなったよ」
と一気に言い、さとしの返事を待たずに走って行ってしまいました。さとしは、まさかあきよから声をかけてくるとは思ってもいなかったので、ぽかんとしました。そして、あきよの言葉を心の中で繰り返して、まさか、聞き間違いじゃないか、と思いました。一人で練習している時や、加藤さんの家では、たびたびソロが成功するようになってきたのですが、クラスのみんなの前で成功したことは、まだ一度もなかったのです。
がんばって練習してる、だって?
さとしは失敗してばかりいるのに、あきよはそう言いました。
ぼくが一人で練習してるところ、見てもいないのに。ぼくがちゃんと吹けたのを、聞いたこともないのに。
「なんでわかったんだろう」
さとしは不思議に思いました。
● ● ●
今日の体育はドッジボールです。隣のクラスと試合をすることになりました。さとし達は、寒さも忘れて走り回っています。一人、また一人とボールに当たって外野に出て、とうとう、両チームとも最後の一人ずつが残りました。さとしのクラスで残ったのはあきよです。
「おい、あきよ、絶対に当たるなよ、逃げるんだぞ。」
ともきが大きな体を揺らしながら叫びました。両方のチームを、ボールが行ったり来たりするたび、歓声が上がります。突然、大きな拍手がわきました。相手チームの残った一人が、さとしのクラスの外野からのボールを受け止めたのです。その子は、あきよに向かって力いっぱいボールを投げつけました。あきよの正面です。あきよは思わず目をつむってボールを抱え込みました。
「取った!」
と誰もが思った瞬間、あきよの手からボールがするりと落ちました。
「やったー!」
相手チームは、ジャンプしたり手を叩いたりして大喜びです。
「あきよちゃん、だいじょうぶ?」
みさとが駆け寄ると、あきよは下を向いて、くちびるをぎゅっとかんでいます。
「どこか痛いの?」
心配そうなみさとに、あきよは首を横に振るだけです。すると、ともきがみさとを押しのけてやってきて、
「ばか! 取らずに逃げていれば勝てたのに。あきよが悪いんだぞ。」
とあきよの肩をどんと押しました。あきよがよろけて転んだのを見て、さとしは思わず二人の間に入り、ともきを睨みつけました。
「そんな言い方するなよ。あきよちゃんだって頑張ったじゃないか。」
クラスのみんなはあっけにとられました。さとしが、仲の悪いはずのあきよをかばったからです。あきよも信じられないというような顔をして、さとしの後ろ姿を見上げていました。
いつの間にか、さとしは自分の音だけでなく、みんなの音も聞けるようになりました。あきよのピアノとさとしのハーモニカが一緒に動くところでは、前は合わずにぐちゃぐちゃになっていましたが、だんだん合うようになってきました。ぴたりと合うと、とても気持ちがいいのです。でもやっぱり、ソロだけは完璧にできたことはありませんでした。
● ● ●
「家で一人で練習したり、加藤さんと一緒だとうまくいくのに、教室でみんなと合わせるといつも失敗するんだ。」
さとしは肩を落として言いました。
「誰だってそうだよ。」
加藤さんはテーブルにカステラを出しながら言いました。練習のあと、加藤さんはよくジュースとお菓子を出してくれるのです。
「一人だとリラックスしてできるけど、誰かに自分の音を聞かれてると思えば、緊張するに決まってるさ。緊張すると、本当はできることも、失敗しちゃったりするんだなあ。」
「じゃあ、どうすればいいの?」
加藤さんはにこにこしながら、さとしのコップにジュースを注ぎました。さとしが困っているのに、加藤さんは笑っています。さとしはちょっと腹が立ちました。
「もう! 真面目に相談に乗ってよ。」
「ああ、ごめんごめん。できるわけがないってあきらめてた最初に比べたら、さとしくんも進歩したなあって思ってね。」
もしかしたら褒められているのかなと思ったけれど、さとしはちっとも嬉しくありません。
「本番の神様って、いると思うかい?」
加藤さんは唐突に聞きました。
「長年、いろんな曲を演奏してきたけど、練習では完璧に弾けても、本番になるとミスをしてしまうことがやっぱりあってね。本番の舞台には魔物がいる、ってずっと思ってたのさ。」
加藤さんは、さとしと一緒の時にはめったにしないことなのですが、珍しくタバコを一本取り出して火をつけました。そして、加藤さんにしてはこれもまた珍しく、饒舌に話し始めました。
「仲良しの笛吹きに、おもしろい奴がいてね。やけに本番に強くて、いつも練習よりも本番が一番いいんだ。ある時、今のさとしくんみたいに、目立つソロをやることになった。本番までの半年間、何度やっても、いつまでたっても、うまくいかない。わたしも含めて誰もが、こればっかりは奴にも無理なんじゃないかと思った。ところがだよ。本番の幕があいてみてびっくりだ。あんなに綺麗に奴のソロが決まったのは初めて聞いた。演奏会が終わってから、みんなで寄ってたかって、奇跡だってからかってやったさ。そしたら、自分には本番の神様がついているから、って涼しい顔してかっこつけやがった。」
加藤さんは、ぷあーっと白い煙を吐き出しました。
「でも、みんな知ってたさ。奴が、陰ですごく努力してたってこと。必死に練習してる姿なんて誰にも見せなかったけど、奴の音を聞けばわたしたちにはわかったからね。」
音を聞けばわかる?
さとしには思ってもみないことでした。
あきよちゃんも、ぼくの音を聞くだけで、ぼくが一生懸命練習してるってことがわかったんだろうか。
「本番の神様がついてるなら、練習なんかせずに遊んでたって大丈夫だと思うだろう? でも、もうこれ以上ないっていうくらい頑張ってた。どうも本番の神様は、誰でも成功させてくれるわけじゃないみたいでね。努力することが条件なんだ。しかも、本人が努力した分を本番で発揮できるようにしてくれるだけで、実力以上にはしてくれないんだなあ。神様にしては怠け者だねえ。でも、魔物がいるって思うより、本番の神様を信じるほうがずっと愉快だ。」
本番の神様。
そんなの聞いたこともない、とさとしは思いました。どんな姿で、どんな顔をしているんだろう。
「奴にね、こっそり教えてもらったよ。本番の神様を呼び寄せる秘訣。知りたいかい?」
「えっ、なになに!?」
思わずさとしは身を乗り出しました。加藤さんは、灰皿にトントンとタバコの灰を落としました。
「演奏がうまくいって、大満足で喜んでる自分を思い浮かべること。」
さとしはぎくりとしました。学校ではいつも、また失敗したらどうしよう、とか、どうせうまくいかないに決まってる、とか考えていたからです。
加藤さんは、ちょっと黙っていました。ゆっくりと煙を吐き出すと、目を細めてつぶやきました。
「なつかしいね。」
そして加藤さんは、急に真顔になって言いました。
「さとしくんには、もしかしたら本番の神様が見えるかもしれないな。」
● ● ●
今日は、ちょっとした事件がありました。みんなの前で、さとしのソロが初めて成功したのです。
「すごーい!」
みさとが目をまるくして言いました。
「さとし、やるじゃん。」
ともきも、ちょっと見直したようです。さとしは、まだ手が震えて、心臓がどきどきしています。ちらっとあきよの方を見ると、あきよは右手の親指と人差し指で小さな丸を作り、片目をつむって見せました。さとしは、泣きたいんだか、笑いたいんだか、自分でもわかりませんでした。
そのあとは、何回やってもさとしのソロは成功しませんでした。でも、さとしはもう、がっかりすることはありませんでした。
● ● ●
「ぼく、家で練習したくないよ。お母さんが曲を覚えてしまって、勝手に歌うんだ。ぼくは難しいところだけ繰り返し練習したいのに、お母さんがどんどん先を歌うもんだから、もうイライラする。」
加藤さんは大笑いしました。 いつものように、さとしは加藤さんの家で練習したあと、ジュースをごちそうになっています。
「音楽会までもうすぐだね。さとしくん、とってもうまくなったから大丈夫だよ。」
その時、玄関のチャイムが鳴りました。「ちょっと待っててね」と言って、加藤さんは玄関へ向かいました。
ふと、いつもは閉まっている部屋のドアが少し開いていることに、さとしは気づきました。以前、間違えてドアを開けようとして怒られた部屋です。ちらりと見ると、加藤さんは玄関で話し込んでいます。隣の山田さんが回覧板を持ってきたようです。遠くに住んでいるお孫さんが昨日まで泊まっていたらしく、山田さんは延々と孫自慢を始めました。加藤さんは、しばらく解放してもらえないでしょう。さとしは急にどきどきしてきました。今なら、こっそりあの部屋を覗いてみることができます。どうして加藤さんがあんなに怒ったのか、覗けばわかるかもしれません。でも、もし見たことがばれたら? さとしは迷いました。立ち上がっては座り、また立ち上がっては座り、そんなことを何度も繰り返しました。ついに好奇心に負けて、ドアの前まで歩いていき、そっと部屋を覗いてみました。部屋の隅に小さな古ぼけた机があり、その上に写真が飾ってありました。女の人が一人で写っています。髪の長い綺麗な人です。その写真の前には、これもまた古そうな、細長い茶色い箱が置いてありました。さとしは、山田さんの話がまだ終わりそうにないかどうか気にしながら、机に近づき右手を箱に伸ばしました。左手は、心臓が飛び出しそうなので、胸を押さえていなければならなかったからです。そして、音がしないよう慎重にゆっくりと開けました。一瞬、はっとするほどの輝きに息を呑みました。中には、古ぼけた箱とは不釣合いなほど美しく磨き上げられた銀色の横笛が入っていたのです。さとしは慌ててふたを閉め、その部屋を出ました。
急に罪悪感に襲われました。元の部屋に戻り座っていると、加藤さんが「お待たせ」と言いながら歩いてきました。さとしは、写真のことも楽器のことも言い出せませんでした。
● ● ●
さとしは、それ以来、加藤さんの家に行っていません。黙ってあの部屋を覗いたことがうしろめたくて、加藤さんの顔を見ることができなかったのです。しかたなく、一人で練習を続けていました。
風の冷たい日でした。さとしはお母さんに頼まれて、駅前の薬局へおつかいに行きました。頼まれたのど飴を買って店の外へ出ると、着物姿のおばあさんが、メモを片手にあっち行っては立ち止まり、こっち行ってはまた戻り、困っている様子です。どうしようか迷いましたが、その顔になんだか見覚えがあるような気がして、さとしは思い切って声をかけました。
「あのう、何かお探しですか?」
おばあさんはさとしを見て、ほっと安心したような顔になりました。
「このお宅を訪ねたいんだけど、道がわからなくて」
そう言って差し出した住所のメモを見て、さとしはぎくっとしました。それは加藤さんの家です。さとしは勿論、加藤さんの家を知っています。案内することもできます。でも、今加藤さんと顔を合わせるのは、ちょっと気まずいのです。
「駅の反対側かしらね」
また不安そうな表情になっているおばあさんを見て、さとしは思わず、
「大丈夫。ぼくが連れて行ってあげる」
と言ってしまいました。
「助かるわ、ありがとう。」
さとしは、おばあさんの手荷物を代わりに持ち、一緒に歩き始めました。
加藤さんのお客さんじゃ、親切にしないわけにいかないじゃないか。玄関まで連れて行ったら、加藤さんが出てくる前に走って帰ろう。
しかし、さとしの予定は狂ってしまいました。アパートの前に来てみると、なんと加藤さんが、一階にある郵便受けを覗きに下りて来たところだったのです。
どうしよう。
さとしは身体が急に固くなるのがわかりました。でも、加藤さんの眼は、おばあさんに釘付けになっています。
「久しぶりね。あなたがどこにいるのか、探すの大変だったのよ。ちょっと上がらせていただくわ」
言葉の出ない加藤さんを横目に、おばあさんはもう階段を上り始めていました。
さとしは慌てて帰ろうとしましたが、驚くべき速さで加藤さんがさとしの腕を掴みました。
「頼む、さとしくん。ちょっとつきあって。あの女の人、苦手なんだ」
いつもの加藤さんと全然違います。しょうがないので、さとしは加藤さんの言うとおりにしました。
加藤さんは、湯飲みを倒したり茶葉をこぼしたりしながら、あたふたとお茶を淹れました。さとしにはジュースです。テーブルの上には、おばあさんの手土産のおしゃれな洋菓子が置かれました。おばあさんと向かい合って座った加藤さんは、まるで先生に怒られている子供みたいにかしこまっています。なんだか変な雰囲気です。第一、おばあさんは、確かに年は加藤さんと同じくらいだけど、着物は高そうなものだし、髪も綺麗に結ってあるし、こんなおんぼろアパートにいるのが全然似合わない人なのです。
「お礼を言いたくて、あなたを探していたの。毎年、お墓に花を供えてくれているのは、あなたでしょう」
「・・・・・・すいません」
「どうして謝るのよ。ありがとうを言いに来たのよ」
おばあさんは少し笑いました。でも、なんだか寂しそう。
その時、さとしは、おばあさんの顔に見覚えがある理由にはっと思い当たりました。
「おばあさんが、あの写真の女の人なの!?」
言ってしまってから、さとしは慌てて口を押さえました。でも、加藤さんは驚いたり怒ったりしません。さとしが写真を見たことは、もうとっくに気づいていたようなのです。
おばあさんは、両手で湯飲みを持ち、ゆっくりお茶をすすると、
「その女の人は、私の妹よ」
と言いました。
だから写真の人と似ているんだ、とさとしは納得しました。
「妹は、加藤さんのお嫁さんになるはずだったの」
そんな話は初耳です。さとしは眼をぱちくりさせました。
「あの子のお葬式の後、あなたは急にいなくなってしまって・・・・・・。でも良かった、今も弾いているみたいだから」
おばあさんの視線は、加藤さんの右手に注がれていました。加藤さんは、服装にはまるで頓着しないのですが、「こうしないとギターが弾きにくくなるから」と、右手の爪だけは常に磨いているのです。
「私も、加藤さんのお嫁さんになりたかったのよ。でも、死んだ妹に勝てっこないって、あきらめちゃった」
加藤さんは、お茶を淹れなおしに台所へ立ち、聞こえないふりをしています。おばあさんはさとしの頭をそっと撫で、
「うちにも、坊やくらいの孫がいるのよ。道案内してくれてありがとうね。・・・・・・じゃあ、そろそろおいとまするわ」
と立ち上がりました。
さとしと加藤さんは、おばあさんを駅まで送りました。最後におばあさんは、さとしにお礼を言いながら握手を求めました。とても暖かい手でした。それから、加藤さんとちょっと長めの握手をして、改札を通って行きました。おばあさんは振り返りませんでした。
おばあさんの姿が見えなくなると、加藤さんは
「かっこ悪いところ、見せちゃったな」
と言いました。
「ううん、そんなことないよ。加藤さん、モテたんだね」
加藤さんは照れたようにちょっと笑いました。
「・・・・・・あの・・・・・・」
さとしは言いにくそうにもじもじしていましたが、いきなり、がばっと膝にくっつくほど頭を下げました。
「写真、見ちゃってごめんなさい!」
「いいんだよ。それより、ご利益があるといいね」
さとしはきょとんとしました。
「音楽会、がんばってね」
加藤さんはさとしの肩をぽんと軽く叩いて、去っていきました。
● ● ●
音楽会当日は、雲ひとつない青空が広がりました。
講堂では、別のクラスの演奏が始まりました。さとしのクラスは、控え室でそれをかすかに聞きながら出番を待っています。楽器の指使いをおさらいする者、人前で上がらないおまじないをしている者、誰もが真剣です。そこへ、みさとがどたばたと走って来て言いました。
「今、みか先生が着いたみたいだよ。」
みんなの顔がぱっと明るくなりました。赤ちゃんは一緒なのか、みか先生はどこの席に座って聞くのか、など、控え室は急ににぎやかになりました。今回はしょうたも、みさとに「走っちゃいけないんだぞ」とは言いませんでした。
「よっしゃー、がんばるぞ!」
音楽会には全く興味のなさそうだったともきが、みか先生の到着を聞いて一番はりきっています。
「頑張ろうね。」
あきよがさとしに、こっそりささやきました。
いよいよ、さとしのクラスの演奏です。さとしたちは、まだ幕の降りている舞台にスタンバイしています。みんな、いつになく神妙な顔つきです。さとしは緊張してのどがカラカラに渇いてきました。
開演のブザーが鳴り、するすると幕が上がりました。
その時です。さとしは「あっ」と小さく叫びました。さとしの目の前を、小さな光るものがふわりと羽ばたくように飛んで、すぐに消えたのです。
本番の神様だ。
さとしは確信しました。体じゅうに、勇気が湧いてきました。ハーモニカをぐっと握り締め、小さく、でもしっかりとつぶやきました。
「絶対に成功する。」
さとしはもう、この曲が嫌いではありませんでした。
そして、演奏が始まりました。(おしまい)